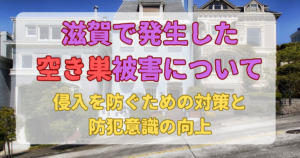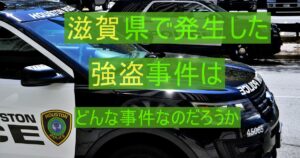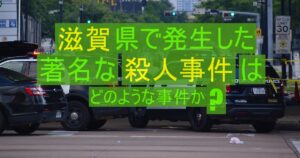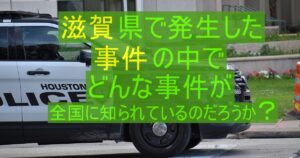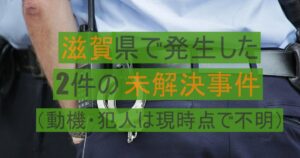研修船「うみのこ」は、滋賀県内の小学生児童の学習・体験を目的としたフローティングスクールです。
大切な子ども達を預ける場でもあるため、保護者の皆さんは「体験中、事件や事故は起こらないだろうか?」と不安に思われることもあるでしょう。
この記事では、研修船「うみのこ」に事件の記録があるかどうか、そして防犯・防災への取り組みを紹介していきます。
※ 情報は2025年4月1日調べのものです
研修船「うみのこ」で大きな事件は【起こっていない】

初就航から2025年4月現在に至るまでの約40年間、研修船「うみのこ」では人命にかかわるような大きな事件は起こっていません。
しかし、インターネットの検索では、「うみのこ 事件」というキーワードが検索の予測単語に上がってくることもあるようです。こうした単語を目にすると、「過去に事件があったのでは?」と不安に思う方もおられるのではないでしょうか。
調べると、平成16年に発生したとされる「研修船うみのこ運航阻害事件」が浮上します。(内容は次項で紹介します)
この事件の記録が、検索キーワードの予測に影響を与えているのかもしれません。
▼ 関連記事|「うみのこ」の学習についてはこちらで紹介しています
研修船「うみのこ」にまつわる事件の記録(平成16年)

海難審判庁採決録の「研修船うみのこ運航阻害事件」の概要を紹介します。
参考:日本財団図書館|平成17年神審第74号 研修船うみのこ運航阻害事件
概要
- 平成16年(2006年)9月21日に、琵琶湖沖島西方沖合にて発生
- 事件区分:安全・運航阻害事件
- 発電機原動機の主機4つの停止により、沖合で航行不能になり救援された
小学生178人や引率者20人を乗せて研修航海を行っていたところ、途中で燃料の供給が無くなった3号主機が停止。その10分後、他の3機も次々と停まってしまい、湖上に取り残されてしまったようです。
主機を再始動できなかったため、救援を呼び、他の船に曳航されました。
安全・運航阻害事件とは
「船舶自体には損害は発生しなかったが、運航が妨げられており危険だった」という状態です。
安全阻害|船舶には損傷がなかったが、貨物の積み付け不良のため、船体が傾斜して転覆等の危険な状態が生じた場合のように、切迫した危険が具体的に発生した場合をいう。
運航阻害|船舶には損傷がなかったが、燃料、清水等の積み込み不足のために運航不能に陥った場合のように、船舶の通常の運航を妨げ、時間的経過に従って危険性が増大することが予想される場合をいう。
引用:国土交通省 海難審判所|海難審判所の裁決で用いられる用語の説明
原因
発電機原動機が停止におちいった原因は主に、下記の2つです。
- 燃料油供給タンクについていた低液面警報装置が、不適切に取り扱われていた
- 納品されていたバイオディーゼル燃料油が、不適切な性質・状態になっていた
燃料油の性質・状態が適切ではなかったために、長い時間をかけて機器の内部で付着。そして、燃料油移送ポンプの働きが阻害されて、燃料油供給タンクに正常に燃料油が送られなくなったのです。
一方、低液面警報装置も正しく機能していなかったため、燃料油供給タンクの残量が少なくなっても確認されることがなかったようです。
結果、燃料油供給タンクに必要なだけの燃料が足りなくなったことで、航行不能になってしまいました。
不審者や事故に備えて、訓練が行われている

多くの児童を乗せて運行する研修船「うみのこ」では、日頃から不審者や事故に備えた訓練も行われています。また、事故に遭わないよう、天候の悪化などに応じて運行スケジュールを変更するなどの対応も取られています。
実際に行われた訓練の取り組み例を紹介します。
不審者を想定した訓練
「停泊した直後に、不審者が侵入してきた」というシチュエーションで実施。船内への情報の共有や、通報の手順、到着した警察官が不審者役の人物を取り押さえるまでの訓練でした。
落水を想定した訓練
「うみのこから児童が湖に落ちた」というシチュエーションで実施。訓練用の人形を湖に落とし、乗組員・引率者が連携して救助し、搬送するまでの訓練でした。
参考:滋賀県教育委員会|令和6年度学習船「うみのこ」落水者救助訓練について
まとめ
- 研修船「うみのこ」では、初就航から今まで、人命に関わるような事件は起こっていない
- 過去にエンジントラブルに関する事件があったよう(平成16年)
- 日頃から防犯・防災に向けた訓練が行われている
日頃からの備えで、「うみのこ」では安全な運航が心がけられているのです。
こうした大人達の取り組みと見守りで、子ども達がこれからも楽しい学習体験をしていけることを願ってやみません。