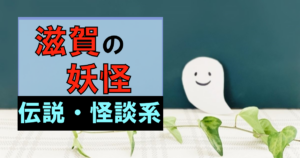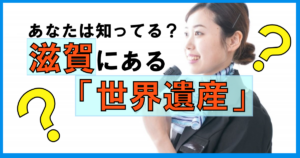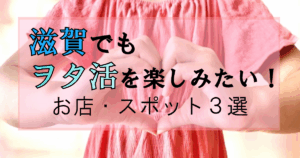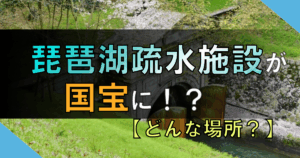日々の暮らしの中で、「野神信仰」「野神さん」という言葉を聞いたことはあるでしょうか? 漢字そのままで意味をとらえると「野の神様」という感じですが、不思議な響きですよね。
リサイズ3-300x300.jpg)
万物全てに神様が宿っている!という考え方は、アニミズムなんでしたっけ? 関係あるのでしょうか?
滋賀でも野神信仰があるそうですよ!
_リサイズ-300x300.jpg)
滋賀で古くから続いている野神信仰とはどのようなものか、軽めに解説していきますね! 地元の風習や民族文化を知れば、ますます滋賀を知るのが楽しくなりますよ!
滋賀にもある!野神信仰・野神さんの風習

滋賀県では長浜市のあたりで古いケヤキの巨木などが「のがみさん」として残され、今も親しまれています。
もう少し堅苦しい言い方では、【野神信仰】ともいいます。
五穀豊穣や守護の願い
野神信仰は土着の民間信仰で、日本各地で見られる風習・民族文化です。古く大きな木などを神様に見立ててお祀りし、五穀豊穣や守りを願うもの。【野神さん】【農神さん】という名前で呼ばれることも。
滋賀の「野神さん」に見られるのは巨木が多いですが、木だけでなく岩や塚の場合もあるそうです。
_リサイズ-300x300.jpg)
都市化した町では珍しいですが、農業地域などでは今もこうした信仰が残っていることもあるんですね。
探してみると、案外身近にもあるかもしれませんよ!
-1-300x300.jpg)
世界中でみられる自然信仰の1つ
野神信仰のように、「自然物を神様・精霊として祀る自然信仰」は世界中にあります。特に、古来から神道が根ざして来た日本では珍しくなく、なじみ深いものともいえるでしょう。
リサイズ3-300x300.jpg)
日本では古く、縄文時代からこうした信仰の形が続いて来たと考えられています。
▼ おすすめ関連記事|山をとうとうと流れ落ちる滝も、神秘的なスポットとして知られていますね!
野神信仰の特徴・祀り方

日本ではどのように野神さんが祀られているのでしょうか? どんな木が選ばれるのでしょうか?
特徴や祀られ方の一例を紹介します。
祀り方の特徴
各集落(村)ごとに集落の出入り口や、境目、分岐などに祀られます。ご神木に巻かれる「しめ縄(注連縄)」が幹にぐるりと巻かれていることもあるので、一目でわかるかもしれませんね。
そばに石碑や石塔、案内板などが設置されていることもあります。
種類
滋賀の「野神さん」では、
- ケヤキ
- スギ
- アカガシ
- シラカシ
などの、真っすぐ高くそびえる木が多いようです。滋賀県長浜市で祀られる木のうち、巨木のものは樹齢数百年と推定されるものもあります。
滋賀の例:野神ケヤキ
長浜市高月町渡岸寺(どうがんじ)で祀られる [野神ケヤキ] も古く、その樹齢はおよそ300年ほどだろうということです。300年前といえば江戸時代の中期頃ですね!
長い年月を経て高く太く成長した巨木は神秘的であり、迫力がありますね。何年も何年も、人々の暮らしとともに時代の移り変わりを見守ってきたのでしょうか。
「野神神社」との違いは?

滋賀県で「野神さん」といわれるものにはもう1つ、大津市の野神神社があります。
こちらは南北朝時代の武将「新田義貞」の妻・勾当内侍(こうとうのないし)の霊を慰めるために建てられたもので、自然物を祀る野神信仰とはまた違うようです。
境内には勾当内侍の墓と伝わるお墓もあります。
-1-300x300.jpg)
南北朝時代とは、現代から約670年ほど前の室町時代です! 戦国時代よりも昔ですよ。
こちらの神社も、遠い歴史を感じますね!
リサイズ3-300x300.jpg)
▼ おすすめ関連記事|滋賀の神社を巡ってみよう! 有名・人気のスポットを紹介しています。
まとめ
この記事では、滋賀でも古くから続く「野神信仰(野神さん)」について紹介・解説しました。
- 野神信仰は自然信仰の1つで日本各地にあり、滋賀県でもみられる
- 滋賀の野神信仰の例では、長浜市にある [野神ケヤキ] などがあげられる
- 大津市に「野神神社」もあるが、こちらは武将の妻を祀ったもの
樹齢何百年も経た木の力強さ・神秘性。野神信仰は巨木や岩を祀り、豊作や安全を願う、長く続けられてきた人々の暮らしに関わりのある風習です。都市化で一見忘れ去られたようでも、今も暮らしの身近に、こうした風習・文化が根付いているのですね!
最後までお読みいただき、ありがとうございます。